事業内容を教えてください。
昭和22年に東京都中央区日本橋で創業した、独立系の鉄鋼一次指定商社です。鉄鋼はあらゆるところで必要とされる素材ですので、お客様の業種は多岐にわたります。また、当社は製鉄メーカーから仕入れた材料を自社工場で加工し、販売までをワンストップで行うという国内で数少ない体制をとっています。そのため、必要な商品や製品のサイズなど、お客様の要望にきめ細かく迅速に対応できる点に強みを持っています。
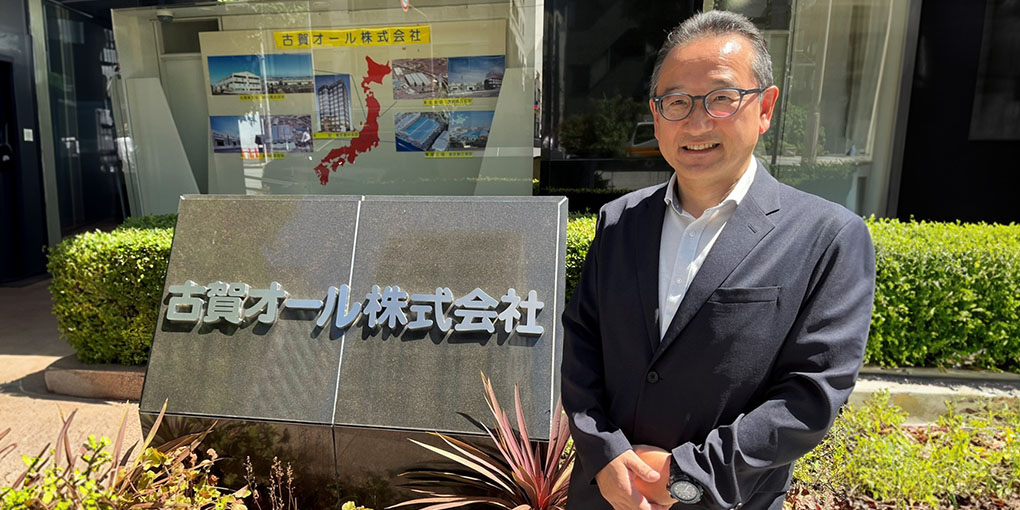

昭和22年に東京都中央区日本橋で創業した、独立系の鉄鋼一次指定商社です。鉄鋼はあらゆるところで必要とされる素材ですので、お客様の業種は多岐にわたります。また、当社は製鉄メーカーから仕入れた材料を自社工場で加工し、販売までをワンストップで行うという国内で数少ない体制をとっています。そのため、必要な商品や製品のサイズなど、お客様の要望にきめ細かく迅速に対応できる点に強みを持っています。
鉄鋼業のCO2排出量は日本全体の14%ほどを占めています。産業部門だと35%ほどとなっており、最もCO2を排出している業界です。
背景は、鉄の製造プロセスにあります。自然界で酸化した鉄鉱石(酸化鉄)から酸素を取り除く作業(還元)を経て鉄を作るのですが、主流は石炭を使った還元方法です。石炭の炭素(C)と、鉄鉱石に含まれる酸素(O2)を結び付かせて酸素を取り除き、鉄を取り出すため多くのCO2が発生し、その量は鉄1トンに対して約2トンにおよびます。当社の排出するCO2に関しても、全体(Scope1-Scope3)のうち98%がScope3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)で、仕入れる鉄に由来するものがほとんどです。
根本策は、製造プロセスを見直すことです。現在、水素還元技術などの、CO2排出の少ない還元方法の研究が進められています。水素(H2)で還元する場合、理論上、排出されるのは水(H2O)だけですので、実現できればCO2の排出をほぼゼロにできます。ただ、実現には多額の資金が必要で、10兆円以上かかるといわれています。
もともと当社の副社長が環境課題について関心が高く、産業界で最もCO2を出しているという課題意識があったことが大きいです。Scope1とScope2に対しては、20年近く前からエクセルで管理していました。
仮に国内製鉄メーカーのCO2排出量をゼロにできたら、鉄鋼業は脱炭素に最も貢献する産業ということになります。昨今の気候変動の状況を鑑みても、脱炭素の取り組みは優先順位として最も高いと思います。
当社は直接鉄の製造には関わっていませんが、国内製鉄メーカーを支援し、さらに国内製鉄メーカーのCO2排出量削減に寄与することが、カーボンニュートラルに最も貢献できる部分だと考えています。そのためには、当社自身がどのくらいCO2を出しているのか、どのように削減の取り組みをしているのかを説明できなければなりません。
当社は、CO2排出量の少ない製鉄を実現するために全力を注ぐことが使命だと位置付け、行動指針にも掲げています。算定の取り組みは、その使命を果たすための一要素だと考えています。
Scope3の算定を始める2ヶ月前くらいにSustanaを紹介していただき、Scope3については初めからSustanaを使って実施しました。
Scope3についてはわからない部分が多く不安もあったので、導入にあたって迷いはありませんでした。大手銀行が提供しているツールでしたので安心感があったこと、当時はまだそうしたツールが多くなかったこともあり、他との比較はしませんでした。

まず、環境省のウェブサイトにある情報を読んで、カテゴリについての勉強から始めました。コンサルなどは依頼せず、ウェブサイトや本を読んで自力で学びました。
Scope3算定の設計ポイントは、数字を正しく把握して理解し、算定に必要なデータが入ってくる仕組みを作ることです。Sustanaを活用して仕組みづくりを行い、算定の体制を整えました。
会社で購入している物品それぞれについて、排出原単位のどの項目に当てはまるのかを考えなければならないところです。どれにも該当しないと思う場合も多いので、自分たちで解釈して決める必要があります。
さらに当社の場合、排出量の98%がScope3のカテゴリ1であるため、その他の2%に対してどこまで精緻に行うのかという線引きに苦労しました。算定結果を将来開示することを意識し、当社としてどういう発信をしていくべきかを考えて線引きを行いました。
Scope3については、算定しなくて良い部分・簡便なやり方で問題ない部分などに関する明確なルールがないため、苦労する面もありました。Sustanaの算定に関する解説動画のコンテンツでは、そのようなことに対する考え方などの情報も提供されており、確認することで精神的に楽になりました。
カテゴリ1については、財務情報や社内の関係部署からデータを確認し、購入したものに対して係数をかけます。
カテゴリ4については、作られた製造所の情報を仕入れ先からいただきます。ただ、製造所から中継地の倉庫までの距離や、そこから当社の工場までの距離については、誰も情報を持っていないので、自分でGoogleマップなどで距離を調べてデータを作りました。また、海上輸送もデータがないため、航路を調べて同じように対応しました。
運送業者からデータをいただく場合、手書きのものがFAXや郵送で送られてくる場合もあります。しかし、データでいただけないと、集計に膨大な時間がかかってしまいます。データで送っていただくようにご協力を仰ぐためには、CO2排出量の算定の先にある、排出を削減する意義をご理解いただかなくてはなりません。鉄鋼業界が置かれている状況や、デジタル化を含めた今後やるべきことをお話し、浸透をはかっています。具体的な取り組みとして、当社でフォームを作り、そちらにデータを入力いただくような工夫もしています。
Sustanaの機能にある算定の基礎知識という動画コンテンツを見ておけば、Scope3算定に対する理解が早まると思います。当社の場合は、何度か算定作業を経験した後にコンテンツを見ることによって解像度が非常に上がり、自信を持って算定できるようになりました。
Sustanaは、対応する排出係数さえ割り出せれば、決まった項目に数字を入れていくだけなので、わかりやすくて使いやすいです。Scope3に対しては知見がないところからのスタートでしたが、最初に導入しておいて良かったと思います。
自分たちが集計したデータを、対外的にアピールしやすい形に可視化してくれるところも、助かる部分だと感じています。

国内製鉄メーカーは日本の製造業を支えており、国内製鉄メーカーの発展は、日本の製造業を盛り上げていくために必要な要素だと当社は考えています。国内製鉄メーカーの収益体質をより良くするためには、当社の在り方の軸をしっかりさせることが大切です。製鉄におけるCO2排出量削減の鍵となる水素還元による製鉄は、莫大なお金がかかります。その資金を捻出するためには、国内製鉄メーカーがしっかり稼いでいかなければなりません。それもただ稼ぐだけではなく、環境に配慮した製品を作る企業が報われるようにする必要があります。
鉄鋼業界の脱炭素における当社の重要な役割は、お客様に環境に配慮された製品を選ぶ意義を伝え、購入していただくことだと思います。そのために、少しずつ社外に向けた勉強会等にも取り組み始めており、今後はもっと活動を広げていきたいと考えています。脱炭素という共通課題をお客様と共有し対話をすることで、お客様との関係も深まる実感があります。そうしたことができるのも、これまでCO2排出量の算定などの取り組みを通じて知見を蓄えてきたからだと思っています。
さらに、これは当社だけでできることではないのですが、環境に配慮したものを作るメーカーが適正な対価を受け取れるように業界の構造を変えていきたいです。直接的ではないですが、まずは国際競争力をつけるために過剰な設備を見直す、労働力不足を補うために効率化を進めるといったことを、同業者と一体となって取り組めればと思っています。