- ホーム
- 法人のお客さま
- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜
- 人事に関する記事
- 36協定とは?2021年からの変更点や締結方法などについて解説
人事
公開日:2022.03.30
36協定とは?2021年からの変更点や締結方法などについて解説
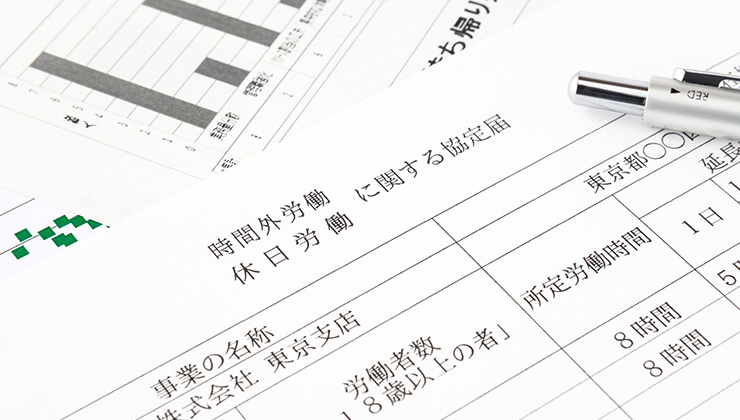
従業員に法定労働時間を超えてまたは法定休日に労働させるには、労使間での「36(サブロク)協定」の締結が必要です。36協定を締結せずに残業を命じることはできません。また、36協定を締結したとしても、無制限に残業をさせることができるわけではありません。
この記事では、36協定の概要と2021年からの36協定届の様式変更のほか、労働基準法に違反した場合の罰則と36協定の締結方法について解説します。
労働基準法第36条にもとづく36協定
従業員が労働できる時間は、法定労働時間として1日8時間、週に40時間までであること、また、法定休日として原則毎週少なくとも1回の休日を確保することが労働基準法で定められています。従業員に法定労働時間を超える労働や法定休日労働をさせる場合は、労使間で36協定を締結しなければなりません。締結後は、所轄の労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定届)を提出することで、法定労働時間を超える残業や法定休日労働が可能になります。
ただし、36協定を締結したからといって、1日8時間を超えた所定労働時間を設定したり(変形労働時間制等特殊な労働時間制度を適用する場合を除く)、恒常的に残業を命じたりすることができるわけではありません。
36協定締結にあたって労使間で取り決める内容
36協定においては、時間外労働の場合、当該時間外労働が発生する具体的理由や業務の種類のほか、対象となる人数、時間外労働時間の原則的な上限などを記載する項目があります。これらの項目を、労使間で取り決めます。
また、原則的な上限を超えて時間外労働を行わせる場合には特別な条項を設け、それが一時的または突発的に発生する業務であることを具体的に示さなければなりません。例えば、「一時的なトラブルへの対応」や「突発的な業務量の増加または仕様変更」など、原則的な上限を超える臨時的な出来事をあらかじめ想定し、労使間で締結します。
36協定の時間外労働の上限時間
36協定を締結した場合の時間外労働の原則的な上限は、月45時間、年360時間です。ただし、特別な事情があって労使間が合意し特別条項を設けた場合は、上限を引き上げることができます。もっとも、36協定を締結したとしても、時間外労働と休日労働の合計時間数が月100時間以上または2ヵ月〜6ヵ月平均して80時間を超えることはできません。
■ 特別条項を設けた場合の時間外労働の上限
| 時間外労働が月45時間を超えることができる回数 | 年6回以内 |
|---|---|
| 時間外労働 | 年720時間以内 |
| 時間外労働と休日労働の合計 | 月100時間未満 |
| 時間外労働と休日労働の平均 | 2ヵ月平均、3ヵ月平均、4ヵ月平均、5ヵ月平均、6ヵ月平均のすべてにおいて、1ヵ月あたり80時間以内 |
36協定の上限の適用が猶予・除外となる事業・業務
36協定の上限が適用されない業務もあります。たとえば、新技術や新商品等の研究開発業務は、特殊な業務を従業員に委ねる必要があるため、36協定の上限が適用されません。ただし、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた従業員には、医師の面接指導を受けさせる必要があります。
そのほか、建設事業、自動車運転業務、医師、鹿児島および沖縄の砂糖製造業については、2024年3月31日まで36協定の上限の対象外とする猶予期間が設けられています。猶予後は、それぞれの事業または業務に応じた上限が適用される予定です。
36協定届の2021年からの変更点
2021年4月1日から、36協定届の様式が変更されました。
36協定を締結する際は有効期間を定めなければならず、期間は1年が望ましいとされています。多くの企業では毎年1回36協定を締結することになるため、新しい様式の変更点についても理解しておきましょう。
なお、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。
使用者の押印および署名の廃止
36協定届の新しい様式では、使用者による押印および署名が不要になりました。ただし、36協定届が労使間で締結する36協定の協定書を兼ねている場合は、労使双方の合意がなされたことが明らかとなる方法(署名または押印など)による必要があります。
従業員代表に関するチェックボックスの新設
36協定届の新しい様式では、従業員の過半数代表者の選出について確認するためのチェックボックスが新設されました。監督者や管理者、使用者の意向で選出された従業員などは、従業員の過半数代表者になることができません。チェックボックスにチェックをつけることで、従業員の過半数代表者として適切に選出された人物であることを明らかにします。
e-Govからの一括電子申請が可能
36協定届は事業所ごとに締結して、それぞれの事業所の所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。従前は、過半数労働組合との間で、各事業場において同一の内容(ただし、事業の種類、名称、所在地、従業員数等を除く)の事項を協定した場合に限り、本社が各事業場分も含めて一括して36協定を届け出ることができましたが、2021年3月29日以降は、その要件が緩和されました。具体的には、過半数労働組合がない場合であっても(過半数代表者が事業場ごとに異なっていても)、国の各府省への電子申請が行える「e-Gov」から電子申請をしたときに限って、本社が一括して届け出ることが可能になりました。
届出先は、本社の所轄の労働基準監督署です。これまで事業所単位で行っていた業務を一括して処理することができるため、業務の効率化につながります。
労働基準法に違反した場合の罰則
36協定の内容に反する残業や法定休日労働をさせた場合、労働基準法違反となります。違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
36協定で締結した内容に反する残業等をさせた場合だけでなく、そもそも36協定を締結せずに残業等をさせた場合も労働基準法違反となります。
なお、労働基準法に違反した場合に罰則を受けるのは、企業と使用者(勤怠管理者や残業を命じる者等)です。
36協定の締結方法及び過半数代表者の要件
36協定は、本社や支店、営業所、工場などの事業所ごとに、使用者と従業員代表の間で締結します。締結後は、掲示板などに掲示したり、書面で交付したりして、該当の事業所で働く全従業員に周知しなければなりません。
なお、従業員代表とは、労働組合もしくは従業員の中から選定された人のことです。従業員の過半数が所属している労働組合がある場合、36協定は使用者と当該労働組合との間で書面により締結します。
一方、上記労働組合がない企業は、従業員の過半数を代表する者を選出して36協定を締結します。従業員の過半数代表者は、下記の条件をすべて満たす必要があります。
<従業員の過半数代表者となる条件>
- ・監督者や管理者ではないこと
- ・使用者(企業)の意向で選出した人ではないこと
- ・36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票や挙手といった民主的な手続きにより従業員選出された者であること
36協定の上限を超えないためには確実な勤怠管理が必要
36協定を締結していても、残業時間の上限がなくなるわけではありません。従業員の権利と健康を守るためには、しっかりと勤怠管理を行う必要があります。しかし、紙などをベースに勤怠管理を行っていては、間違いが起こることもあるでしょう。部署や従業員ごとの残業時間がわかる勤怠管理システムなどを導入し、労働時間をしっかり把握できるようにしておくことが大切です。
SMBCグループが提供する「PlariTown」では、労務管理や人事管理など業務効率化に資する、さまざまなデジタルサービスをご案内しています。
勤怠管理システムの導入を検討している方など、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。
(※)2022年3月30日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。
(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。