- ホーム
- 法人のお客さま
- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜
- 人事に関する記事
- 裁量労働制とは?制度の対象やメリットについて詳しく解説
人事
公開日:2022.03.30
裁量労働制とは?制度の対象やメリットについて詳しく解説

テレワークや副業を導入する会社が増加し、時間や場所、業務遂行の方法にとらわれない多様な働き方が選べるようになりました。こうした時代背景の変化に伴い注目を集めているのが「裁量労働制」です。
ここでは、裁量労働制の対象となる業務や、導入のメリットおよび要件について解説します。
裁量労働制とは「みなし労働時間」で賃金を支払う制度のこと
裁量労働制は、従業員が実際に働いた時間にかかわらず、「みなし労働時間」分、働いたものとみなす制度です。みなし労働時間は、それまでの労働時間の状況等を踏まえ、対象業務で通常必要とされる時間をあらかじめ労使協定や労使委員会の決議により定めます。
例えば、1日のみなし労働時間を「8時間」とした場合、業務が6時間で終了しても、業務を終えるまで9時間かかったとしても、8時間労働したものとみなされ、これに対する賃金を支払うことになります。
従業員には、「所定の労働時間働くこと」ではなく「成果を出すこと」が求められるため、極端にいえば、求められる成果さえ出せれば何時から仕事を始めても、何時に仕事を終えても構いません。
会社が与えるのはミッションのみで、そのミッションをどう遂行するかは従業員個人の裁量に任せられます。ただし、裁量労働時間制であっても、会社が設定したみなし労働時間が1日8時間以上になる場合(1日のみなし時間を積算して1週40時間以上となる場合を含む)、会社側は時間外手当を支払わなくてはなりません。また、法定休日や深夜帯に勤務した場合も、別途残業代が発生します。
勤務時間と成果が比例しない専門業務や企画業務を行う従業員にとって、勤務開始や勤務終了を厳密に制限しない裁量労働制は、非常に効率的な制度だといえるでしょう。一方で、会社が労働時間を厳格に管理することができず、労働時間の配分を従業員の判断に委ねる形となりますので、長時間労働の温床になりかねない側面もあり、導入にあたっては慎重な判断が求められます。
裁量労働制とフレックスタイム制の違い
裁量労働制は、出退勤時間が自由であるという点でフレックスタイム制と似ているように見えます。しかし、両者には下記のような違いがあり、まったく別の労働時間制度です。
・裁量労働制
裁量労働制は、「みなし労働時間=労働時間」とする制度です。実際に働いた時間がみなし労働時間以下だったとしても、反対にみなし労働時間以上に働いたとしても、みなし労働時間を労働したものとみなされ、基本的には労働時間が多いか少ないかで給料は変わりません。
・フレックスタイム制
フレックスタイム制は、1日の始業時刻、終業時刻の判断を従業員が自由に決められる制度です。ただし、裁量労働制のように1日の労働時間をみなす制度ではなく、会社は実際に働いた1日の実労働時間に応じて給料を支払う必要があります。
裁量労働制を導入するメリット
裁量労働制を導入することで、企業にどのようなメリットがあるのでしょうか。代表的な2つのメリットについてご説明します。
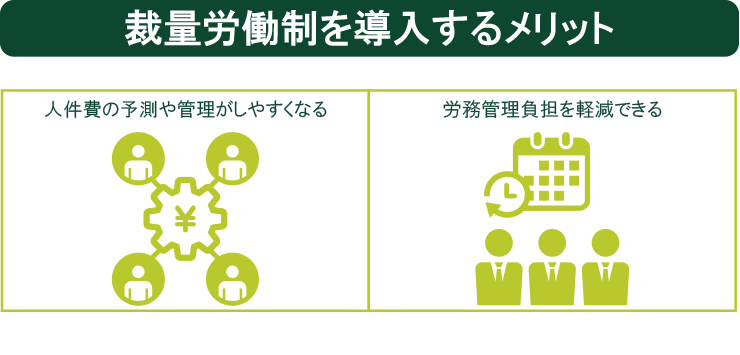
人件費の予測や管理がしやすくなる
前述した通り、裁量労働制はみなし労働時間を設定して賃金を計算する仕組みです。残業代は、基本的にはみなし労働時間に含まれるため、従業員数とみなし労働時間からおおよその人件費を、まえもって算出することが可能です。
人件費は、企業経営の安定性を測る重要な指標ですから、早い段階での予測・管理を可能にし、人件費を適正な割合に近づけられる裁量労働制の導入は、大きなメリットといえるでしょう。
また、裁量労働制を導入すれば、従業員も「早く成果を出して早く帰ろう」と、効率を重視するようになります。すると、生産性の低さを長時間勤務でカバーする従業員に対して残業代を支払わずに済み、結果として生産性の向上と人件費の削減につながります。
労務管理の負担を軽減できる
労務は、従業員が安心して働ける環境を作るため、労働環境や福利厚生の整備、給料計算などの作業を担っています。中でも、毎月変動する給与について、残業代を計算し、所得税や住民税を天引きする給与計算は、複雑で負担が大きいものです。
裁量労働時間制なら、休日・深夜などの特殊な時間に勤務した場合を除き、基本的には別途実績に応じて残業代を支払う必要がありません。みなし労働時間から算出した金額を固定給(裁量手当等の固定残業代を含む)として処理することで、労務管理の負担を大幅に軽減することができるでしょう。
裁量労働制の対象となる業務および導入要件
裁量労働制は、どの職種に対しても導入できるわけではありません。導入対象となる業務は限定的であり、大きくは、専門業務型と企画業務型の2種類に分かれます。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制とは、業務の内容を理解して実行するのに専門的な知識が必要であり、使用者側が仕事の進め方や時間配分などを指示するのが難しい業務を行う従業員に対して、みなし労働時間労働したものとみなすことができる制度です。
この制度は、下記の19の専門業務が対象となります。
<専門業務型裁量労働制の対象となる業務>
- ・新商品もしくは新技術の研究開発、または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務
- ・情報処理システムの分析または設計の業務
- ・新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務、または放送番組制作のための取材もしくは編集の業務
- ・衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- ・放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
- ・広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に関わる文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- ・事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握、またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- ・建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現、または助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- ・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- ・有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれにもとづく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- ・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- ・大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
- ・公認会計士の業務
- ・弁護士の業務
- ・建築士(一級建築士、二級建築士および木造建築士)の業務
- ・不動産鑑定士の業務
- ・弁理士の業務
- ・税理士の業務
- ・中小企業診断士の業務
専門業務型裁量労働制を導入するためには、導入する事業場ごとに、労使間の労使協定において次の事項を定める必要があります。また、当該労使協定は、所轄の労働基準監督署に届け出て、従業員に周知する必要があります。
<専門業務型裁量労働制に関する労使協定で定める事項>
- ・対象業務(上記19の業務から選択)
- ・みなし労働時間(対象業務に従事する従業員の労働時間として算定される時間)
- ・対象業務を遂行する手段および時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する従業員に具体的な指示をしないこと
- ・対象業務に従事する従業員の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
- ・対象業務に従事する従業員からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
- ・有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- ・把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置および苦情処理措置の記録を協定の有効期間中およびその期間の満了後3年間保存すること
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制とは、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて、企画、立案、調査および分析を行う従業員に対して、みなし労働時間労働したものとみなすことができる制度のことです。
この制度は、下記の8つの業務が対象となりえます。
<企画業務型裁量労働制の対象となりうる業務>
- ・経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査および分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
- ・経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査および分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
- ・人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査および分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
- ・人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査および分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
- ・財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査および分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
- ・広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査および分析を行い、広報を企画・立案する業務
- ・営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査および分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
- ・生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に関わる市場の動向等について調査および分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務
企画業務型裁量労働制を導入するためには、従業員を代表する委員と使用者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、導入する事業場ごとに、労使委員会において次の事項を決議する必要があります。また、当該決議をしたことを所轄の労働基準監督署に届け出て、対象労働者から同意を得る必要があります。なお、上記労使委員会の決議から6ヵ月以内に同署に定期報告もしなければなりません。
<企画業務型裁量労働制に関して労使委員会で決議すべき事項>
- ・対象となる業務の具体的な範囲
- ・対象従業員の具体的な範囲(5年以上の職務経験を有し、職能資格◯級以上の者等)
- ・労働したものとみなす時間
- ・使用者が対象となる従業員の勤務状況に応じて実施する健康および福祉を確保するための措置の具体的内容
- ・使用者が対象となる従業員からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
- ・本制度の運用について従業員本人の同意を得なければならないことおよび不同意の従業員に対し不利益取扱いをしてはならないこと
- ・決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
- ・企画業務型裁量労働制の実施状況に係る従業員ごとの記録を保存すること(決議の有効期間中およびその満了後3年間)
裁量労働制の導入は、制度の整備から
裁量労働制を導入するには、社内体制の整備とルールづくりから取り組む必要があります。さまざまな会社の例を参考にしながら、スムーズな導入を目指しましょう。
SMBCグループが提供する「PlariTown」では、労務管理や人事管理など業務効率化に役立つ、さまざまなデジタルサービスをご案内しています。
裁量労働制の導入を検討している方は、ぜひ「PlariTown」をご利用ください。
(※)2022年3月30日時点の情報のため、最新の情報ではない可能性があります。
(※)法務・税務・労務に関するご相談は、弁護士や税理士など専門家の方にご相談いただきますようお願い申し上げます。