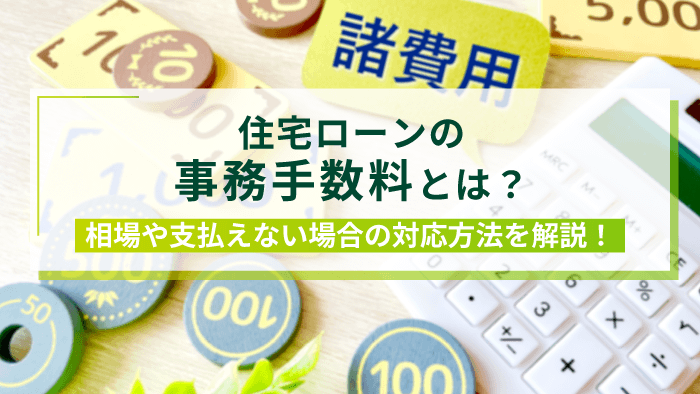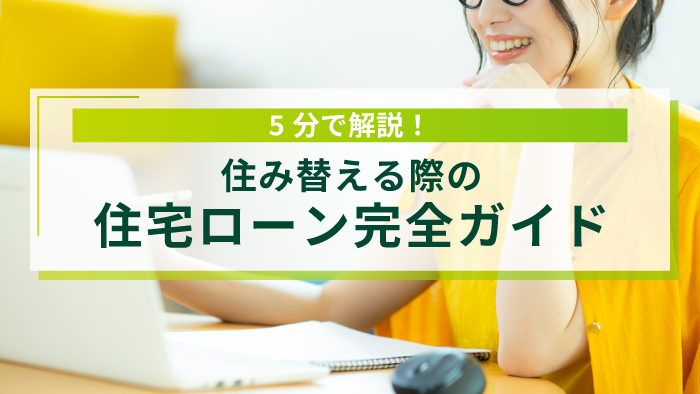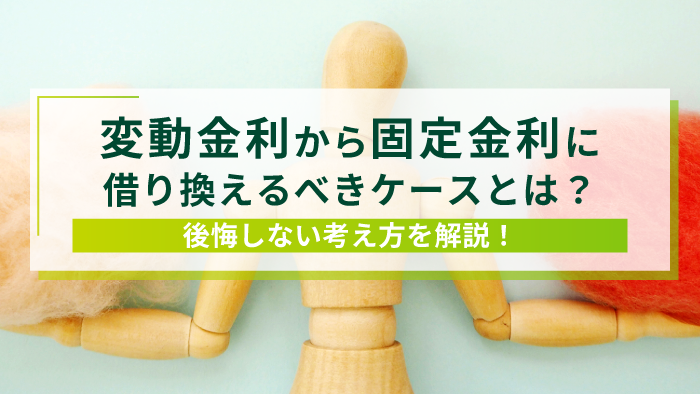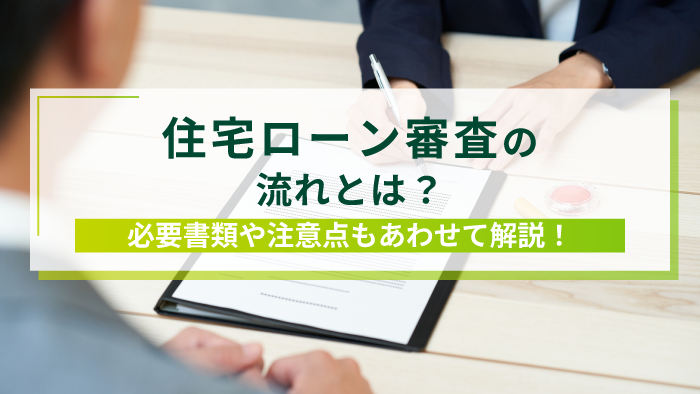住宅ローンの事務手数料とは
住宅ローンの事務手数料は、ローン契約時の手続き費用として金融機関に支払う必要があります。金融機関によって「取扱手数料」「融資手数料」など呼び方は異なりますが、大きく分けて以下の2種類存在します。
それぞれ順に解説していきます。
定額型
定額型の事務手数料は、借入額に関係なく一定額を支払う方式として広く採用されています。一般的に3~5万円程度の手数料が設定されており、借入額が高額になる場合は定率型と比べて割安になる可能性があります。
ただし、定額型では事務手数料とは別に保証料が必要となることが多いのが特徴です。保証料は借入額に対して一定の割合で計算されるため、実質的な負担は増加します。
手数料が安く見える定額型でも、総合的なコストを考慮して判断する必要があります。保証料や金利も含めた比較検討が重要になるでしょう。
定率型
定率型の事務手数料は、借入額に対して一定の割合で計算される方式で、現在の住宅ローン市場では最も一般的な形態となっています。
多くの金融機関では借入額の2.2%(消費税込)程度に設定されており、例えば3,000万円を借り入れる場合、66万円の事務手数料が必要となります。
一見すると高額に感じられますが、定率型の場合は通常、保証料が金利の中に含まれるため、トータルでのコストを考えると必ずしも高いとは限りません。
また、借入額が少ない場合は定額型より総支払額を軽減できるケースが多いとされています。
住宅ローンの事務手数料と合わせて保証料も確認する
住宅ローンの事務手数料を検討する際には、必ず保証料についても確認が必要です。多くの金融機関では、定率型の事務手数料を採用している場合は保証料が金利の中に含まれるため、定額型を採用している場合は別途保証料が必要となる傾向にあります。
保証料には、一括払いの外枠方式と借入金利に金利が上乗せされる内枠方式があります。外枠方式では借入期間と借入額に対して一定の割合で計算され、内枠方式では一般的に年0.2%程度が上乗せ金利として設定されています。保証料は数十万円程度必要になるため、決して小さな金額ではありません。
外枠方式は毎月のローン返済額をできるだけ抑えたい方に向いていますが、保証料としてまとまった金額の初期費用を負担します。一方、内枠方式は借入当初の費用負担こそ少ないものの、総支払額は外枠方式よりも多くなります。さらには、借入額に比例して毎月の返済額も増えます。
ただし、金融機関によっては定額型でも保証料が不要なケースもありますので、住宅ローンの総コストを正確に把握するためにも、事務手数料と保証料の両方を含めた諸費用の確認を怠らないようにしましょう。
住宅ローンの事務手数料が払えない場合はどうすべき?
住宅ローンの事務手数料の支払いが難しい場合でも、以下のような対応方法があります。
それぞれ順に解説していきます。
住宅ローンに組み込む
住宅ローンの事務手数料を借入額に組み込む方法は、初期費用の負担を軽減できる一般的な対処法です。
この方法のメリットは、まとまった現金を用意する必要がなく、月々の返済という形で分割して支払うことができる点です。例えば、物件価格3,000万円に対して事務手数料が66万円の場合、3,066万円の住宅ローンを組むことで対応可能です。
ただし、住宅ローンの借入額が増加することで金利負担も大きくなり、返済期間全体での総支払額は増加します。
また、金融機関によっては諸費用の組み込みに上限を設けている場合もあります。
諸費用ローンを新たに組む
住宅ローンとは別に諸費用専用のローンを組む方法は、事務手数料の支払いに柔軟に対応可能な選択肢の一つです。事務手数料・保証料だけでなく、仲介手数料や火災保険料、登記費用なども含めて一括で借り入れることができます。
諸費用ローンの返済期間は通常の住宅ローンより短めに設定されていることが多く、金利も住宅ローンより高めに設定されているのが一般的です。
ただし、住宅ローンに組み込む場合と比べて返済期間が短いため、総支払額を抑えられる可能性があります。また、住宅ローンと別枠で借り入れることで、将来的な借り換えや繰り上げ返済の際の手続きがシンプルになるというメリットもあります。
事務手数料以外に発生する諸費用も把握しておくべき
住宅ローンを利用して住宅を購入する際には、事務手数料の他にも多くの諸費用が発生します。
| 印紙税 |
- 借入額が1,000万円超5,000万円以下:2万円
- 借入額が5,000万円超1億円以下:6万円
|
| 団体信用生命保険料 |
|
| 火災保険料・地震保険料 |
建物の構造、耐火性能、地域、補償内容、補償金額、保険期間によって保険料は異なる |
| 不動産取得税 |
|
| 登録免許税 |
<所有権移転登記>
- 不動産の固定資産税評価額の0.4%もしくは2%(本則税率)
<抵当権設定登記>
|
| 登記代行手数料 |
|
| 仲介手数料 |
|
これらの諸費用の合計は、物件価格の数%から10%程度になることも珍しくないため、住宅購入前に詳細な資金計画を立てることが重要です。
印紙税
印紙税は、住宅ローン契約書に貼付が必要な収入印紙にかかる税金で、借入額に応じて段階的に税額が定められています。
例えば、借入額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円超1億円以下の場合は6万円となります。
この費用は、契約時に必ず必要となる法定費用の一つです。印紙税は、消費税のような還付制度がなく、また住宅ローン控除の対象にもならないため、全額が実質的な負担となります。
住宅ローン以外にも、不動産売買契約書や建築請負契約書にも印紙税が必要となるため、これらを含めた総額を事前に把握しておくことが賢明です。近年では電子契約の普及により、印紙税が不要となるケースも出てきていますが、金融機関や不動産会社によって対応は異なります。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が死亡または所定の高度障害状態となった場合に、残りの住宅ローンが弁済される保険です。
基本的な保障内容の保険料は住宅ローンの金利に含まれていることが多いですが、三大疾病特約や八大疾病特約などの追加保障を選択する場合は、別途保険料が必要となります。
保険料は年齢や健康状態、借入額、保障内容によっても変動し、例えば40歳で三大疾病特約を付帯する場合、月々数千円から1万円程度の追加保険料が発生することもあります。
火災保険料・地震保険料
火災保険への加入は住宅ローンを組む際の必須条件となっており、建物の保護と債権保全の両面で重要な役割を果たします。 保険料は建物の構造、耐火性能、補償内容、補償金額などによって大きく変動します。保険期間は1年から最長5年まで選択可能です。
地震保険は任意ですが、近年の自然災害の増加により加入を検討する方が増えています。鉄筋コンクリート造の場合であれば、火災保険料は年間数千円~1万円、地震保険料は年間1〜2万円程度が一般的です。木造住宅の場合は火災・地震のリスクが高くなるため、より高額の保険料がかかります。
火災保険料と地震保険料とも建物の所在地や構造によって料金が大きく異なるため、事前に確認しておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税の一つです。固定資産税評価額に対して原則4%の税率が適用されますが、住宅用地の場合は様々な特例措置があります。例えば、新築住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円が控除され、実質的な税負担が軽減されます。
軽減措置の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があり、申請書の提出が必要な場合もあります。一般的な価格帯の住宅であれば非課税要件を満たすため、不動産取得税はかからないケースも多いです。税額が数十万円といった高額になることは稀ですが、不動産取得税の支払い時期は住宅取得日の半年から1年後と後日になりますので、事前に税額を確認し資金計画に組み込んでおく必要があります。
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記の際に必要となる国税です。土地・建物それぞれについて登録免許税が課され、税率は登記の種類によって異なります。所有権移転登記の本則税率は固定資産税評価額の2%ですが、新築住宅の取得にかかわる所有権移転登記の税率は0.4%になります。
それ以外にも、一定の要件を満たせば軽減税率の適用を受けられます。また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記にも借入額の0.4%(本則税率)の登録免許税が必要です。
借入額が3,000万円のときは、抵当権設定登記として12万円の登録免許税が必要となります。
登記代行手数料
登記代行手数料は、不動産の所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定登記を司法書士に依頼する際に発生する費用です。通常、不動産購入時には様々な登記手続きが必要であり、これらの手続きは専門的な知識が求められます。そのため、多くの場合、司法書士に依頼することになります。
登記手続きの内容や物件の状況によって費用は変動しますが、10万円前後が目安となります。
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合は、金融機関の指定する司法書士に抵当権設定登記を依頼するのが一般的です。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社に支払う成功報酬で、物件の売買価格に応じて宅地建物取引業法で上限が定められています。具体的には、売買価格の3%+6万円(消費税別)が上限となっており、例えば3,000万円の物件であれば、最大で96万円(消費税別)となります。
ただし、売主が直接販売する戸建てやマンションには仲介手数料がかかりません。
仲介手数料は決して安い金額ではありませんが、良質な物件情報の提供や価格交渉、契約手続きのサポートなど、専門家のサービスに対する対価として考える必要があります。
住宅ローンにかかる諸費用を節約する方法2つ
住宅ローンの諸費用を抑えるための方法は、実は様々な選択肢が存在します。ただし、むやみに費用を削減するのではなく、将来のリスクも考慮した上で賢明な選択をすることが重要です。ここでは2つの方法を紹介します。
それぞれ順に解説していきます。
火災保険を見直す
火災保険の保険料は、補償内容や保険期間の設定によって大きく変動する可能性があります。例えば、建物と家財の両方を補償する場合と建物のみの補償とでは、年間数万円の差が生じることもあります。
特約についても水災補償や類焼損害特約など、住んでいる地域によっては必要性を吟味することで保険料を抑えられる可能性があります。保険期間は5年など1年超の長期契約を選択することで、最大10%前後の割引率が適用されるケースもあります。
また、同じ補償内容でも保険会社によって保険料が異なるため、複数の保険会社の見積もりを比較検討することをおすすめします。ただし、補償内容の見直しは、居住地域の災害リスクや建物の構造、家族構成などを総合的に考慮して行うことが重要です。
頭金を増やす
頭金を増やして借入額を抑えることは、諸費用の削減に大きな効果があります。特に定率型の事務手数料や保証料は、借入額に応じて計算されるため、頭金を増やして借入額を減らすことで、これらの費用も比例して減少します。
例えば、借入額を500万円減らした場合、定率型2.2%の事務手数料であれば11万円の節約になります。また、借入額が少なくなることで、金利上昇の影響を受けにくいメリットもあります。
さらに、頭金を増やすことで毎月の返済額も抑えられ、長期的な返済負担の軽減にもつながります。ただし、予期せぬ支出に備えて、手元に適切な額の預貯金は残しておく必要があります。
住宅ローンを利用して住宅購入の資金計画を立てる際は、将来のライフイベントを見据えた資金の確保と、諸費用の削減のバランスを考慮することが大切です。