- ホーム
- 法人のお客さま
- Business Navi 〜ビジネスに役立つ情報〜
- 企画に関する記事
- サステナビリティとは?企業が取り組むメリットや指標、事例等を紹介
企画
公開日:2022.05.30
更新日:2023.11.14
サステナビリティとは?企業が取り組むメリットや指標、事例等を紹介

最近、「サステナビリティ」という言葉を耳にすることが増えています。しかし、具体的にどのような目的で使われている言葉かご存じでしょうか。
今後、継続的に企業活動を行うには、サステナビリティを意識した経営が求められると言われています。そこで今回は、サステナビリティの意味やCSR・SDGsとの違いの他、企業がサステナビリティに取り組むメリット等を、事例と併せてご紹介します。
サステナビリティとは?
サステナビリティ(sustainability)とは、環境や経済等に配慮した活動を行うことで、社会全体を長期的に持続させていこうという考え方です。「Sustain(維持する、持続する)」と「Ability(〜する能力)」を組み合わせた造語で、日本語では「持続可能性」と呼ばれます。
持続可能性を意味するサステナビリティ
サステナビリティという文字が初めて登場したのは、1987年「環境と開発に関する世界委員会」が発表した報告書「我ら共有の未来(Our Common Future)」です。同報告書では、将来の豊かさを損なうことなく現在のニーズを満たす「持続可能な開発(Sustainable Development)」を中心的な課題として取り上げ、意識改革を促しています。
その後、1992年に開催された地球サミットで世界的に広まり、2015年に国連で採択された「SDGs」へと繋がっていきました。
このように、サステナビリティは元々環境保護の文脈で用いられる言葉でしたが、近年は企業が果たすべき社会的責任と結び付けて語られることが増えています。企業には、自社における目先の利益だけでなく、環境や経済等に与える影響を考慮した事業活動が求められているのです。
サステナビリティにおいて重視される3つの観点
サステナビリティは、社会の様々なシーンにあてはまる概念であり、あらゆる分野で必要とされる考え方です。特に企業活動においては、「環境保護」「経済開発」「社会開発」の3つの観点に基づく取組が重視されています。
<企業活動において重視される3つの観点>
・環境保護(Environmental Protection)
環境保護とは、人間の経済活動によって引き起こされる環境問題に対応し、負荷を軽減して長く良好な状態を保つための取組です。温室効果ガス対策や森林保護、海洋生態系保護、電力消費量削減、生物多様性の保全等が該当します。
・経済開発(Economic Development)
経済開発は、地域社会の生産性拡大、経済成長を目的として行われる開発のことです。労働環境の整備や、社会保障の拡充、貧困問題への対応等が含まれます。
・社会開発(Social Development)
生産第一主義のもとで行われる経済開発に対して、医療、教育、雇用、住宅、社会福祉といった様々な側面から人間の生活環境を向上させるための開発を、社会開発と言います。労働環境にも深く関係するジェンダー平等、ダイバーシティ等への対応の他、難民問題等への貢献が求められます。
サステナビリティとCSRの違い
サステナビリティとよく似た意味の言葉に、CSRがあります。CSRは、「Corporation Social Responsibility(企業の社会的責任)」の頭文字を取った言葉です。CSRとサステナビリティは似た概念ですが、CSRは対象が企業に限られています。
通常、営利企業は自社の利益のために企業活動を行いますが、自社の利益だけを追求するのでなく、消費者や取引先といったステークホルダー(利害関係者)の要求に応えたり、社会環境への配慮を行ったりすべきであるという考え方がCSRです。
具体的には、「自然環境を汚染する物質を排出しない」「安全性に配慮した商品を開発する」「社会貢献のための活動を行う」といったことが該当します。
サステナビリティとSDGsの関係性
SDGsは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の頭文字を取った言葉です。2015年9月に国連サミットで採択された、サステナビリティのための具体的な17個の目標がSDGsです。また、それぞれの開発目標には、さらに具体的な取組を示す「ターゲット」が定められています。ターゲットは、全部で169個に及びます。
「サステナビリティと言っても、具体的に何をしたらいいのかわからない」という場合は、SDGsに貢献できる活動を心掛けてみましょう。そうすれば、自然とサステナビリティに繋がっていきます。
サステナビリティを測る指標・指数
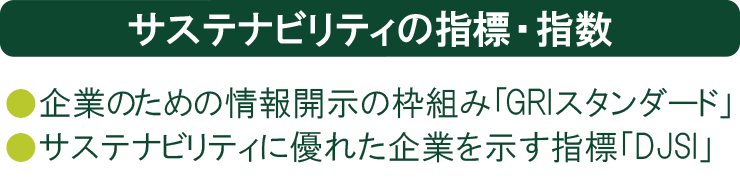
企業がサステナビリティを推進する際は、どのような項目を基準とするべきなのでしょうか。ここでは、サステナビリティを測る代表的な指標・指数を見ていきます。
GRIスタンダード
GRIスタンダードとは、2016年に定められた国際基準です。GRIスタンダードのガイドラインでは、サステナビリティという抽象的な概念が具体的な指標として可視化されています。GRIスタンダードは、企業のサステナビリティに対する客観的な貢献度の測定と情報開示のためのフレームワークです。GRIスタンダードを活用すれば、自社のサステナビリティへの取組を外部へ説明しやすくなるでしょう。
DJSI
DJSI(The Dow Jones Sustainability Indices)とは、金融市場指数を幅広く提供しているアメリカのS&P Dow Jones Indices社と、サステナビリティ投資に特化した投資会社であるスイスのRobecoSAM社が、1999年に共同開発した投資家向けのインデックス(指数)です。DJSIは、世界の主要企業のサステナビリティを評価し、総合的に優れた企業をDJSI銘柄として選定しています。
持続可能性に優れた企業の間では、DJSI銘柄に選定されることは大きな名誉となります。また、投資家や外部ステークホルダーに対するアピールにもなるため、DJSI銘柄選定を目指す企業は日本でも多くなっているようです。
サステナビリティを意識した経営を行うメリット
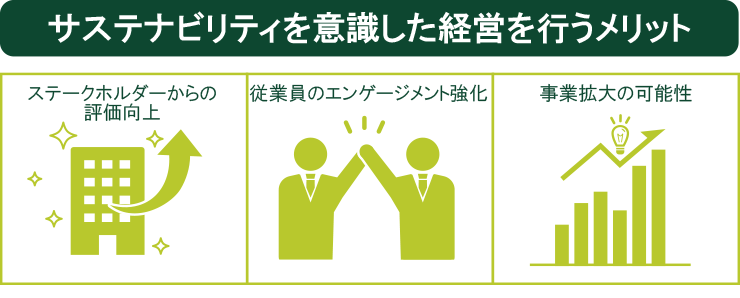
サステナビリティを意識した経営を行うと、環境問題や社会問題の解決に貢献できます。また、企業活動の在り方について考え、持続可能な社会を目指していくことは、経営上でもメリットがあります。
ここでは、社会貢献の他に、サステナビリティを意識した経営を行うことで得られるメリットを3点ご紹介しましょう。
ステークホルダーからの評価向上
ステークホルダーからの評価向上は、経営を行う上で非常に重要な要素です。サステナビリティを意識した経営を行うことで、消費者や取引先、株主等から「社会的な責任を果たしている企業」というイメージを持ってもらうことができ、評価の向上に繋がるでしょう。
こうした評価向上は、売上アップや取引先の拡大、リピーターの獲得等といった多くのメリットにも繋がります。
従業員のエンゲージメント強化
サステナビリティの指標のひとつであるGRIスタンダードには、「社会」の項目として「雇用」「労使関係」「労働安全衛生」「研修と教育」「ダイバーシティと機会均等」といった項目が設定されています。従業員の雇用環境を明らかにすると共に、労働安全衛生や必要な研修の提供等を行うことで、働きやすい職場環境を作れるでしょう。
また、企業がサステナビリティを意識した経営を行うことは、従業員にとっての誇りにも繋がります。企業イメージが高まれば、それだけ従業員も働きがいを感じやすくなります。
こうした理由から、サステナビリティは従業員が企業に対する愛着や貢献の意志を深める「エンゲージメント強化」にも繋がるのです。
事業拡大の可能性
サステナビリティへの取組から新たなアイディアが生まれたり、新たな技術の開発に成功したりすることもあります。また、サステナビリティのための活動が取引先の拡大に繋がる可能性もあるでしょう。
サステナビリティを意識すると、これまで目を向けたことがなかった分野や、関わりのなかった企業との新たな出会いも生まれるため、事業拡大の可能性は大いにあります。
企業のサステナビリティ事例
ここでは、サステナビリティに取り組んでいる企業の事例を、3つご紹介します。他社の事例を参考に、自社でできることがないか検討にお役立てください。
家具メーカーのサステナブルな施策
ある大手家具メーカーでは、サステナブルな素材を選ぶだけでなく、ユーザーがサステナブルな生活を送れる施策にも力を入れています。例えば、使い捨てプラスチックの段階的な廃止やフードロス対策、不用になった家具の買取サービス等です。この企業は、これらの多彩な取組によって、環境に負担がかからず、快適に暮らせる持続可能な社会を目指しています。
さらに、この企業は、2030年までに完全な循環型ビジネスを実施するという目標も掲げています。長く使える家具を作り、不用になったら再利用し、最終的には素材として新たな製品を生み出すというサイクルが実現すれば、環境への負荷を大きく減らすことができるでしょう。
カフェチェーン店のエシカルな調達
「エシカル(倫理的)な調達」とは、原料の生産国や生産者に対して適正な条件で取引をすること(フェアトレード)や、自然環境破壊に繋がらない調達等を指します。
エシカルな調達は、特に途上国での原料調達が多いコーヒーやチョコレートの生産でよく話題に上がります。
コーヒー豆の産地では、生産者の貧困や自然破壊などが問題になってきました。そこであるカフェチェーン店は、環境や社会、経済、品質といった面で責任を持って栽培され、エシカルに取引されたコーヒー豆を買い付けるようにしました。エシカルな調達に力を入れ、生産者の生活を支援するとともに、生産者や地域の自然を守ることに力を入れているようです。
製薬会社による開発途上国に向けた治療薬の開発
「必要な人に必要な医薬品をひとつでも多く届ける」という理念を持つ製薬会社は、開発途上国や新興国で蔓延する疾患の治療薬の開発の他、現地の人々への啓蒙活動等を行っています。世界では治療に必要な医療や医薬品を受けられない多くの人が、疾患のリスクにさらされています。そこで、同社は医薬品アクセスの向上のために手に取りやすい価格設定の検討といった取組も行ったそうです。
また、そのような活動に興味や関心を持った人々から、「世界中の人々の健康に力を入れている企業で働きたい」という思いを抱かれ、海外の優秀な人材の獲得にもつながりました。